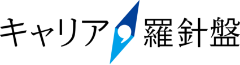ミドルシニアの羅針盤レター2025-03

|
ミドルシニアの羅針盤レター 2025#3
|
第3回:なぜ「あなたはどうしたいのか?」が響かないのか
|
|
トレスペクト教育研究所の宇都出雅巳代表に、キャリア自律における「聞く」ことの重要性について語っていただきました。
全4回シリーズの第3回目です。 |
前回お伝えした、「意識の矢印(→)を相手に向け続けて聞く」──この聞き方は、通常のキャッチボール的な会話では起こらないものです。そして、コーチングにおける「聞く」とは、単に話さないで(我慢して)聞くことではないとおわかりいただけたでしょう。
今回は、こうした「聞く」を土台とするコーチングとは何か。その本質をお伝えすると同時に、その限界はどこにあるのか、その限界をフォローするものとして、動機づけ面接(MI)を紹介します。
■もう一つの「聞く」:「人」に焦点を当てて聞く
まず最初に、「意識の矢印(→)を相手に向け続けて聞く」ことに加えて、もう一つ、通常の会話における「聞く」とは違う、コーチングにおける「聞く」をお伝えします。これがある意味、コーチングの本質だからです。
それは「事柄」でなく「人」に焦点を当てて聞く、という聞き方。
これを知ったのは、今から24年前、私がコーチングに最初に触れたワークショップの初日、しかも始まって間もなくのことでした。
「人の話の聞き方には二つあります。一つは事柄に焦点を当てて聞く聞き方、もう一つは人に焦点を当てて聞く聞き方。コーチングでは主に人に焦点を当てて聞きます」
私にとって、講師のこの言葉は衝撃でした。私はそれまで「事柄」にばかり焦点を当てて聞いていたからです。
たとえば、部下が「週末に読んだ本、面白かったですよ」と話しかけてきたとき、私は「どこが面白かった?」「他に何が書いてあった?」と質問して聞いてはいたものの、私の焦点は本という「事柄」にあり、相手という「人」ではありませんでした。「意識の矢印(→)」は自分に向いていたと言えます。私が聞いていたのは、相手が話したいことではなく、自分が聞きたいことだったのです。
もちろん、「事柄」も大事です。仕事において、「人」よりも「事柄」に焦点を当てることが大事な場面は数多くあります。ただ、相手という「人」に焦点を当て、「意識の矢印(→)」を相手に向け続けることで、その人の価値観や思い込みに触れることができるのです。
「事柄」に焦点を当て、相手が「事柄」の説明をするのを聞いていても、そこで深い気づきは起こらず、コーチングにはなりません。「人」に焦点を当て、相手が自分の考えや思いを語って、初めてコーチングになるのです。
「意識の矢印(→)」を相手に向け続けて聞く。そして、「事柄」だけでなく「人」に焦点を当てて聞く。これがコーチングの本質なのです。
■「あなたはどうなりたいの? どうしたいの?」──コーチングの限界と弊害
ただ、このコーチング、その限界、そして弊害もあります。というのも、コーチングはもともと、プロのコーチと、そのサービスに対価を払ってでも受けようとするクライアント、つまり、「変わりたい」という意志を持つ人との間で行われる関係を前提としたものだからです。
典型的なコーチングの質問として、「あなたはどうなりたい? どうしたい?」というものがあります。まさに「人」に焦点を当て、未来へ向かう王道の質問です。
この質問は、コーチングのクライアントであればいいですが、「変わりたい」と思っているとは限らない部下、特にシニアミドルの「すねている層」に対して、この質問を投げかけると、「なぜそんなことを話さないいといけないんだ」と抵抗・防御の姿勢を取らせてしまいます。
実際、最近では「Willハラ(スメント)」という言葉も聞かれるようになってきました。本来、コーチングにおける「あなたはどうなりたい? どうしたい?」という問いかけは、相手の主体性や内発的動機を引き出すものとして非常に重要です。しかし、相手によってはプレッシャーを感じてしまうのです。
ここで私が注目しているのが、動機づけ面接(MI:Motivational Interviewing)というカウンセリング技法です。MIはもともと、薬物依存やアルコール依存などの問題を抱える人への支援として開発されたカウンセリング手法です。
特徴的なのは、支援を受けにきた人の多くが「自分の意思で変わりたい」と思っているわけではないという点です。多くの場合、本人は周囲に促されてしぶしぶやってきた、という状態です。つまり、MIは、「まだ変わる準備が整っていない人」にこそ届く可能性を持つアプローチであり、企業においてもミドルシニア層へのキャリア支援や1on1のあり方を再考するヒントになるのです。
このMIの特徴は、そうした相手を変えようとするのではなく、相手の語る言葉や沈黙に丁寧に耳を傾け、「変わりたくない気持ち」も含めて尊重しながら、少しずつ「変わりたい気持ち」を育てていく点にあります。
なぜ、MIは相手を変えようとしないか。それは、「変わりたい」でも「変わりたくない」という人は、相手から変えようとされる(アドバイスや変わる方向への質問などをされる)と、それを否定したり、抵抗したりして、防衛的になる可能性が高くなるからです。
MIでも「質問」は行いますが、それよりも重視されるのが「聞き返し」です。これは、相手の語ったことに対して、評価や判断を挟まず、言葉を繰り返したり言い換えたりして返す技法です。
たとえば、「最近、やる気が出ないんですよね」に対して「やる気が出ない感じが続いているんですね」、「正直、このままでいいのかって、ちょっと悩んでます」に対して、「“このままでいいのか”っていう気持ちが、どこかにあるんですね」。
このような聞き返しによって、「聞いてもらえた」「わかってもらえた」という感覚が育まれ、それが対話の安心感と信頼感につながります。MIでは、こうした聞き返しが「質問」よりも多くなるよう意識することが推奨されています。
「質問」はある特定の方向に会話を導いていくことになりますが、これは相手が自ら自分自身を探索することを制限してしまう危険があります。聞き返しが多くなればなるほど、相手自身による探索と気づきを促すことができるからです。
このように、ミドルシニアのキャリア自律支援においては、コーチングを土台にしつつも、コーチングの限界をMIなどのカウンセリング技法の考えを取り入れて補正していくことが重要になっていくのです。
最終回となる次回は、「聞く」を土台にしたこうしたコーチング、MIを集合研修や企業内の場でどのように応用していくかを解説します。
|
【筆者プロフィール】
宇都出 雅巳(うつで まさみ) トレスペクト教育研究所 代表 東京大学経済学部、ニューヨーク大学スターンスクール(MBA)卒。東洋経済新報社、コンサルティング会社、シティバンク銀行を経て、2002年にトレスペクト教育研究所を設立。以来20年以上にわたり、1対1のコーチングならびにコーチング研修、マネジメント研修に従事し、10,000人を超えるビジネスパーソンと向き合う。2007年、国際コーチ連盟認定PCC(プロフェッショナル・サーティファイド・コーチ)取得。コーチングに加え、さまざまな心理療法、認知科学の知見も生かした独自の「聞き方」を提唱。著書は『絶妙な聞き方』(PHP研究所)、『仕事のミスが絶対なくなる頭の使い方』(クロスメディア・パブリッシング)など25冊を超える。訳書に『コーチング・バイブル―人の潜在力を引き出す協働的コミュニケーション』(共訳、東洋経済新報社)、『応用インプロの挑戦―医療・教育・ビジネスを変える即興の力』(共訳、新曜社)がある。 |
当メールマガジンは一般社団法人定年後研究所が総合監修し、配信運営は株式会社星和ビジネスリンクが行っております。